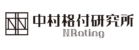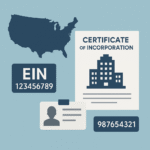シリーズの狙い
米国の関税圧力と中国市場の減退により、日系企業は新たな市場を模索せざるを得ない状況にあります。
本シリーズでは、地域ごとに注目市場を取り上げ、日系企業が強みを発揮できる分野と市場参入のPros(機会)・Cons(リスク) を整理していきます。
今回は「アジア:インド・ベトナム」を取り上げ、次回は「欧州」を特集します。
各国分析の共通小見出し
- 基本概況
- 日系企業が強みを発揮できる産業
- Pros(市場機会)
- Cons(リスク要因)
- 米国関税との関係性
- その他(当該国特有の要素)
- 業界別有望度ランキング
- 魅力のまとめ
インド
基本概況
インドは2023年に国連推計で中国を上回り、世界最大の人口大国となりました(約14億人)。名目GDPは世界5位ですが、複数の国際機関は2030年頃に世界第3位へと浮上すると予測しています。経済成長率は堅調で、IMFは2025年実質GDP成長率を6.5%と見込んでおり、主要国の中でもトップ水準です。
日系企業が強みを発揮できる産業
二輪車や自動車での存在感はすでに大きく、ホンダやスズキが確固たるシェアを確保しています。加えて、都市化に伴う建設資材・化学製品の需要は拡大中です。さらにIT分野では、インドの豊富な人材と日本企業のデジタル化ニーズが補完関係にあり、アウトソーシングや共同開発の機会が広がっています。
Pros(市場機会)
中間層の拡大が進み、耐久消費財や住宅、自動車への需要は今後も増加が見込まれます。英語が広く通用し、ビジネス環境の透明性は新興国の中でも高い水準です。政府は「Make in India」に加えて「Production-Linked Incentive(PLI)」制度を導入し、電子機器やEV、医薬品などへの製造投資を積極的に支援しています。
Cons(リスク要因)
最大の課題はインフラ整備の遅れで、電力や物流の不安定さが事業コストを押し上げます。州ごとに異なる規制や税制は複雑で、進出企業にとって負担が大きい点も変わりません。2024年の総選挙後、モディ政権が続投したものの、政策の継続性や外資誘致のペースには不透明感が残ります。また、韓国や中国企業との競争激化も避けられない課題です。
米国関税との関係性
インドは2019年に米国から「GSP(一般特恵関税制度)」の優遇撤廃を受け、繊維や宝飾品など一部輸出産業は影響を受けました。ただし中国のように「輸出依存度が極めて高い構造」ではなく、インド経済の核は強力な内需です。むしろ米国が中国からの輸入を代替する候補地として評価されており、米国関税リスクのマイナス面より、代替需要のプラス面が勝る市場構造を持ちます。
その他
政府はEV普及を後押ししており、電動二輪・三輪車向け補助政策「FAME-II」の延長や強化が議論されています。さらに、日本の円借款によるデリー・ムンバイ産業大動脈や都市メトロ整備といった大型インフラ案件が進行中で、日本企業の参入機会が拡大しています。
業界別有望度ランキング(インド)
- 自動車・二輪車(特にEV関連)
- ITサービス・デジタルアウトソーシング
- インフラ・建設(鉄道・都市開発)
- 化学・素材(セメント、樹脂、特殊化学品)
- 消費財・小売(家電、食品)
魅力のまとめ
インドは確かにインフラ不足や規制の複雑さといった課題を抱えています。しかし、それを上回るだけの人口規模と経済成長力を有し、米国関税圧力を受けてもなお「内需と輸出の二重の強み」が揺るぎません。むしろ米中摩擦が強まるほど、中国依存からの代替市場としての存在感は増しています。「長期的な需要拡大+代替供給拠点」という二重の優位性がインド市場の魅力です。
ベトナム
基本概況
ベトナムの人口は2024年時点で約9,900万人台、平均年齢は31歳と若年層が厚く、人口ボーナスが続いています。GDPに占める製造業比率は約26%で、輸出依存型の産業構造が特徴です。サムスンは輸出の約20%を担う最大の外資企業で、Apple関連のFoxconnやLuxshareも北部を中心に投資を拡大しています。
日系企業が強みを発揮できる産業
繊維や靴など労働集約型の産業は依然として強みを持ちますが、電子部品や精密機械の分野では、日本の部品供給網と現地生産基盤が補完関係を形成しています。食品加工産業も伸びており、日本の安全・品質基準に基づいた製品は国内需要と輸出の両面で競争力があります。
Pros(市場機会)
賃金水準は依然として中国より低く、チャイナ+1戦略の最大候補として注目されています。米国や欧州とのFTA(CPTPP、EVFTA)は、衣料品や農水産品の輸出拡大に大きな恩恵をもたらしています。さらに、ハイテク産業やグリーンエネルギーに投資優遇を与える政策も追い風となっています。
Cons(リスク要因)
賃金は上昇傾向にあり、沿岸都市部では最低賃金が月額350〜400米ドルに達しつつあります。人材面では中間管理職不足が続いているものの、外資系大学や職業訓練機関の進出により徐々に改善が進んでいます。2023年以降は汚職防止政策の強化により、電力セクターを中心に規制の不透明さやプロジェクト遅延が発生しました。
米国関税との関係性
ベトナムは米国の対中関税で最も大きな恩恵を受けた国のひとつで、米国輸入シェアを急増させました。その一方で、トランプ政権期には「迂回輸出」や原産地偽装の懸念から監視対象となり、反ダンピング調査も増加しています。再び米国が強硬な関税措置を取れば、繊維や家具といった輸出依存の高い分野は打撃を受ける可能性があります。しかし、CPTPPやEVFTAを通じて市場を分散できるほか、日本企業にとっては完成品輸出よりも部品・中間財供給で参入余地が広く、サプライチェーン再編の受け皿としての地位は揺るぎません。
その他
地場自動車メーカーVinFastは2023年にNASDAQに上場し、2025年には米国販売の拡大を本格化させています。日本の自動車部品企業にとっては提携機会であると同時に競合リスクでもあります。また、物流課題は依然残るものの、北部ハイフォン港の拡張や南部ロングアン港の開発が進行しており、輸送環境は改善しつつあります。
業界別有望度ランキング(ベトナム)
- 電子部品・精密機械
- 労働集約型製造(繊維・靴)
- 食品加工・農業関連
- ロジスティクス・サプライチェーンサービス
- グリーンエネルギー・再生可能エネルギー
魅力のまとめ
ベトナムは米国関税の警戒対象となるリスクを抱えていますが、それを補うFTAネットワークと立地優位性があります。賃金上昇の影響も見られるものの、中国に比べれば依然としてコスト競争力があり、サプライチェーンの再編における主要拠点であることは揺るぎません。「低コスト+輸出アクセス+政策支援の三拍子」がそろった市場として、ベトナムは今後も日系企業にとって有力な進出先です。
おわりに
インドとベトナムはいずれも、米国関税による圧力と中国市場の減退を背景に、日本企業が成長余地を求める最重要市場です。米国関税は確かにリスク要因ですが、両国にはそれを凌駕するだけの 構造的な魅力 があります。
重要なのは、単に市場を選ぶことではなく、現地で誰と組み、誰と競合するかを明確にすることです。
中村格付研究所では、各国における 販売候補先・提携候補先・競合企業のリストアップ を通じ、企業が海外市場で成果を出すための実務的支援を行っています。
次回は「欧州編」として、中東欧やスペインなど、日系企業に新たな機会をもたらす市場を解説します。