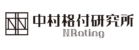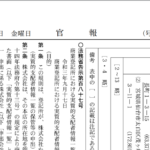信頼とリスク、その“境界線”
企業が取引の意思決定を行おうとする際、誰かからの紹介は有力な情報です。しかし、その“信頼”だけに身をゆだねると、大きなリスクを見逃すことが少なくありません。今回は、身近な2つの事例をもとに「関係性重視が招く落とし穴」を振り返り、実務で役立つチェックポイントをご紹介します。
1.個人VS企業――“あの人だから”が招いた巨額未払い
2025年8月6日、東京商工リサーチが報じた歌手・長渕剛さん(株式会社オフィスレン代表)と、イベント会社ダイヤモンドグループのトラブル。2023年に結んだツアー運営契約で得られるはずだった約2億6,000万円が未払いとなり、長渕さん側から破産申立てにまで発展しました。
このケースでは、恐らく業界の中における特有の仲間内感がマイナスに作用し、相手企業の財務状況や支払実績をきちんと確認しないまま巨額の業務を丸投げしてしまった点が最大の問題と考えられます。さらに、支払スケジュールや保証条項があいまいなまま契約を締結したことで、問題が起きた際に回収手段が限られ、2億円を超える使途不明金をめぐる法的手続きが長期化してしまいました。
教訓としては、どんなに関係性が強い相手でも、必ず第三者データで客観的に裏付けを取り、契約書には支払条件や担保・保証の仕組みをしっかり盛り込むことが不可欠です。
–
2.BtoB“紹介ルート”の闇――商社経由のワナ
メーカーが総合商社を通じて海外輸出を行う際、商社は自社の与信管理部門がリスクを検知すると、即座に取引を停止または縮小することがあります。一方でメーカー側は「紹介された取引先だから安心」と考え、自社での与信調査を省略しがちです。
しかし、商社がリスク回避のために撤退した時点で、その取引先の支払能力はすでに低下しているケースがほとんどです。メーカーが後追いで新たな顧客を開拓しようとしても、一朝一夕には見つからず、商社経由で販売していた先との取引を継続しようとするバイアスが生じます。「もともと商社がやっていたのだから」という理由でその販売先との取引を継続した場合、既に商社が手を引く程信用程度が悪化していることがあり、多額の不良債権が発生してしまうリスクが大きくなります。
このような状況を避けるには、やはり自社の与信基準に基づいて別途調査を実施し、取引条件や与信限度を自ら設計する姿勢が求められます。
実務ですぐ使える――与信管理チェックリスト
1. 情報の“二重取集”
信用調査会社から得られる詳細な財務データや支払遅延・訴訟情報は、非常に価値のある一次情報ですが、それだけに頼るのは避けたいところです。なぜなら、市場の動きや業界特有の要因は自社の取引履歴や担当者の肌感覚からしか得られない情報も多いためです。そこで、信用調査会社のレポートをもとに、自社の過去取引データや営業担当者からのヒアリング結果をクロスチェックすることで、リスクの見落としを防ぎましょう。
2. 与信枠と保証の明文化
取引を開始する際には「どの程度の金額までリスクを許容するか」「支払期日はいつか」「万一の際の担保や保証は何か」といった条件を、必ず契約書に具体的な条項として落とし込みます。たとえば、支払が遅延した場合の延滞金率や、一定額以上の取引には第三者保証人を付けるなど、回収メカニズムをあらかじめ設計しておくことで、トラブル発生時にも動きやすくなります。
3. 定期モニタリングの仕組み化
新規取引先だけを審査して終わり、というのは与信管理の盲点です。既存顧客についても、四半期ごとに売上・利益・自己資本比率などの財務指標をチェックし、もし異変があればアラートを発動する仕組みを構築しましょう。さらに、支払遅延履歴や業界ニュースも併せて追跡することで、顧客の経営状況の変化をいち早く察知できます。
4. 社内横断チームの編成
与信判断は営業だけ、あるいは経理だけの仕事ではありません。営業・法務・経理が一堂に会し、共通フォーマットで評価基準を共有することで、誰が担当しても同じクオリティで与信審査ができるようにしましょう。定期的な勉強会やワークフローの見直しを通じて、組織全体で「与信管理は自分ごと」という意識を醸成することが重要です。
おわりに
「人や紹介への信頼」はビジネスの潤滑油ですが、それだけに頼りすぎるのは危険です。信用調査会社のデータと自社基準を掛け合わせ、リスクの芽を早期に摘むことで、安心して長期的に取引を続けられる体制を築きましょう。
中村格付研究所では、与信管理体制の構築支援やリスク評価ツールの提供を行っています。ご相談はお気軽にどうぞ。次回のブログもお楽しみに!